(1)都道府県、市区町村、社会福祉協議会を対象に、福祉避難所マニュアル作成研修や講師派遣を実施
BCP策定ラッシュが終わり、想定通り、自治体や社会福祉協議会からのBCP作成研修への問合せおよび実施依頼は激減した。福祉避難所や防災対策に関する講師派遣の問合せはこれまで通り寄せられているが、講師費用が定額に満たないものが多い。これらは、これまで通り実施場所や内容から上級コーチ・認定コーチを選定し、先方と繋いで直接対応をしていただいた。
上級コーチ・認定コーチに繋ぎ実施いただいたもの:
神奈川県、高知県、大分県、山梨県内の支援学校、埼玉県幸手市、横浜市金沢区、岐阜県可児市、大阪府藤井寺市、東京都荒川区内の小学校、情熱クラブ、他
福祉避難所マニュアル作成研修等の研修については、本年も(一財)消防防災科学センターからの委託事業を受託することができ、8県で実施した。開催自治体との連絡や講師調整を担当する事務局メンバーを継続して増員したことで、調整等はスムーズに実施することができた。また研修準備についても、引き続き資料・研修機材準備を担当する事務局メンバーを設けることができ、滞りなく実施することができた。研修資料については、共通部分と各回の個別部分に分けることで、印刷数を減らす工夫ができるため、来年度は改良を行いたい。
BCPや福祉避難所開設・運営を机上で訓練するために確立した「福祉避難所図上訓練(旧福祉避難所エクササイズ)」は、福祉避難所マニュアル作成研修の後期研修に組み込み実施することができた。福祉避難所図上訓練の指導ができるコーチの増員が、急務である。
(2)研修講師のできる「福祉防災認定コーチ」に加え、実務を行う「福祉BCP管理者(2級)」を育成する
上級コーチ・認定コーチ・福祉BCP管理者(2級)メンバーに対して、河崎認定コーチが能登半島地震での体験について執筆された本などの情報提供を行った。
当会コーチ等に対して、ご自身の経験や専門性を活かして指導いただく講師との連携は進んでいない。人選、依頼するテーマなどのまとめを行い、名称を決めた上で、依頼をしていく必要がある。
福祉防災認定コーチ
2024年度は、研修を実施することができなかった。認定間もないコーチについては2回のOJTが実施できるよう、研修担当事務職員が調整を行い、OJTが終了したコーチがサポート講師として出講できるようになった。
福祉BCP管理者(2級)
2024年度は、研修等を実施することができなかった。
(3)広報体制の強化
FMサルース「サロン・ド・防災」のスポンサー、ぼうさいこくたいや首都防災ウィークでの広報は継続して実施している。
日本災害福祉研究会に特別会員(賛助)が設置されたことを受け、申し込みを行いホームページ内にバナーを設置いただいた。
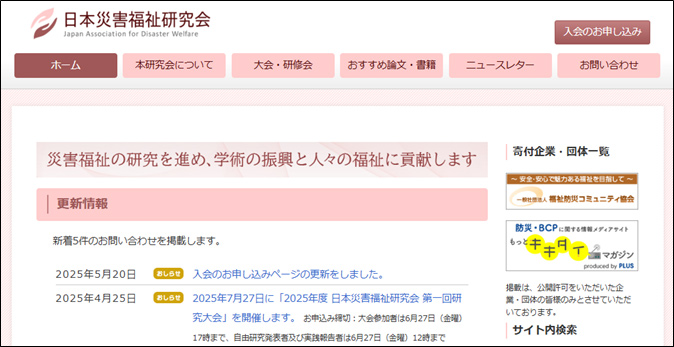
ホームページ内での福祉避難所マニュアル無償配布は継続しており、2024年度は122件のダウンロードがあった(開始時よりトータルで765件)。
協会案内のパンフレットについては、ぼうさいこくたいを中心に配布を行った。また、「みんな元気になる福祉避難所」に関するパンフレット作成を行い、印刷物を作成することができたため、今後のイベント等で配布を行っていく。
(4)能登半島地震における福祉避難所実態調査を実施
令和6年能登半島地震における福祉避難所の実態について、アンケート・ヒアリングを実施することができた。引き続き調査・ヒアリングを行い、福祉避難所マニュアルの改訂を行うと共に、今後に向けた発信を行っていく。
また全国での更なる福祉避難所整備の「呼び水」として、「企業版ふるさと納税を活用した福祉避難所整備事業」を展開できるよう努めているが、2024年度も残念ながら事業を実施できなかった。今後の営業戦略として、作成したパンフレットを使いながら営業活動を依頼するファンドレイザーとの調整を行っており、来年度以降の活躍を期待する。
(5)防災スタートBOX、福祉避難所開設BOXの販売
(社福)埼玉福祉会の協力を得て、災害発生後の初動対応をスムーズに進める防災スタートBOX、福祉避難所開設BOX及び福祉BCPひながたセットの販売を続けている。福祉避難所開設BOXの説明は、消防防災科学センター研修等で継続して行っており、2024年度も通年にわたり福祉BCPひながたセットの購入があった。
(6)福祉防災コミュニティの維持・発展
個人会員は64名となった(前年度、61名)。能登半島地震へのボランティア活動を通じて、個人会員への入会があった。
会員全員へのLINE WORKSのアカウント発行については、事務局体制の改善が難しく進んでいないが、上級コーチ・認定コーチのアカウント利用については事務局メンバーとの対面研修の際に使用方法の共有を行うことができたため、使用頻度が上がった。
法人正会員10施設、法人賛助会員1法人の目標に対しては、達成できていない。
(7)被災地支援
令和6年能登半島地震に関して、フェリシモ㈱「もっとずっときっと基金」からの支援で行った施設への支援金を全て支払うことができた。また活動報告書をまとめ、フェリシモ㈱へ提出、ホームページにアップいただくことができた。秋には福祉避難所の情報を提供いただいた6市町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市)へ訪問し、支援の終了報告を実施、本活動を終了することができた。
また支援を行った施設を対象に、アンケートやヒアリングの実施を行い、論文等として発表する準備を進めることができた。
内閣府が実施している「ボランティア交通費補助金」を活用し、穴水町で活動するレスキューストックヤードと協働し、延べ35人が被災地でのボランティア活動を行った。
(8)「安全・安心魅力施設」の認定
「安全・安心魅力施設」の認定基準に沿って、2施設の認定を実施することができた。
